宿場で歴史と文化を学ぶ
長久保宿
当初は依田川沿いに宿場が設けられていましたが、大洪水のため寛永八年(1631)以降に段丘上の現在地に移り、本陣・問屋を中心に東西方向に「横町」が形成されていき、得意なL字型の町並みとなりました。
長久保宿には寛政(1739)以降、四十軒前後の旅籠屋があり、中山道信濃二十六宿のなかでは、上位に位置する数を誇りました。
和田宿
中山道の最高地点にして最大の難所といわれた和田峠(標高約1600メートル)を控え、隣の下諏訪宿までは五里十八町(約22キロメートル)、峠との標高差は800メートルほどもあったため、逗留する諸大名らの行列や旅人も多く、長久保宿と同様に、信濃二十六宿のなかでは規模が大きい宿場町でした。
幕末の文久元年(1861)3月、本陣ほか宿場の大半が火災で焼失してしまいますが、この年の11月には皇女和宮の御下向が控えていたことから、幕府より二千両ほど拝借して町並みを復興させ、この大通行を無事に迎えました。
町指定 長久保宿本陣石合家
江戸時代を通じて本陣と問屋を勤め、四代当主のもとには真田信繁(幸村)の娘が嫁いでいます。
大名などの賓客が使用した「御殿」は17世紀後半の構築と推定され、中山道中では最古の本陣遺構であるといわれています。
国史跡 和田宿本陣
文久元年の大火後に再建された間口12棟(母屋)で和田宿最大の建造物です。明治維新後は、長年、役場や農協の事務所として昭和59年まで使用され、同61年から5ヶ年の歳月をかけて往時の姿に復元されました。
国史跡 唐沢一里塚
江戸より51番目の一里塚で、対で現存しています。
国史跡 永代人馬施行所
冬季に和田峠を越える旅人にお粥と焚火を、牛馬には年間を通して桶一杯の煮麦を無償で施しました。
この記事に関するお問い合わせ先
産業建設課 商工観光係
〒386-0603
長野県小県郡長和町古町4247番地1
電話番号:0268-75-2085
お問い合わせはこちら







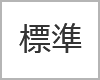
更新日:2024年03月29日