防災
現在、災害を完全に予測することや回避することはできません。しかし、常日ごろから、いざという時、家族があわてずに行動できるよう次のことを話し合い、家族ぐるみで災害に対する備えをおこたらず、いつでも対応できるよう用意をしておけば、被害を防ぐことができます。
家族1人ひとりの役割分担
日常の予防対策上の役割と、災害時の役割の両方について決める。寝たきりの高齢者、病人、小さな子供がいる場合は、誰が保護を担当するかなども話し合う。
家屋の危険箇所チェック
家の内外をチェックして危険箇所を確認し合う。放置できない危険箇所については、修理や補強を行う。
家屋の安全な配置と転倒防止策
家具の配置換えによって家の中に安全なスペースをつくれないか工夫する。
また、家具の転倒や落下を防ぐため固定する。
災害時の連絡方法や避難場所・避難経路の確認
災害時の家族間の連絡方法と最終的に落ち合う場所をどこにするか決める。それに伴い、避難場所と避難経路等を確認する。
非常持ち出し品のチェックと入れ替え・補充
家族構成を考えながら、必要な品がそろっているかをチェックする。定期的に新しいものと取替える。(使用期限のある非常食、水、乾電池等)
災害時の燃料供給について
これまで全国で発生した大規模災害において、発災直後からガソリンスタンドに燃料を求める行列ができるなどの混乱が生じた例がありました。家庭においても、日ごろから自動車の燃料を満タンにしておく、暖房用燃料をプラスで購入しておくなど、災害時に備えましょう。
住民拠点SS(サービスステーション)
平成28年4月の熊本地震において、災害時における燃料供給拠点としてのSSの役割が再認識されたことを踏まえ、自家発電設備を備え、災害による停電においても可能な限り被災地の住民に燃料供給を行う「住民拠点SS」の整備が資源エネルギー庁により進められています。
いざという時、不安による買いだめ、買い急ぎの無いよう、日ごろからお近くの住民拠点SSの場所を確認しておきましょう。







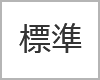
更新日:2025年02月18日