汚泥堆肥中のPFOS(ピーフォス)・PFOA(ピーフォア)分析結果の公表について
長和町生ごみ堆肥化処理施設で作られた生ごみ堆肥中のPFOS・PFOA濃度は、78μg/kgです。
※μg(マイクログラム)=100万分の1グラム
この分析の結果について、農林水産省が令和6年4月に公表した「汚泥肥料中のPFOS及びPFOAについて」の内容と照らし合わせたところ、長和町汚泥堆肥を使用して生産された農作物を摂取しても、健康への悪影響はないと考えられます。
今後、堆肥をご希望される町民の皆様におかれましては、ご理解をいただいた中でのご予約をお願いいたします。

汚泥肥料中のPFOS及びPFOAについて(出典:農林水産省・一部抜粋)
汚泥肥料中の PFOS 及び PFOA について(外部リンク)
長和町汚泥堆肥分析結果について
分析報告書(PFOS・PFOA) (PDFファイル: 645.9KB)
採取日:令和7年3月6日
検査日:令和7年4月3日
分析:株式会社 科学技術開発センター(計量証明事業登録:長野一般・環境第31号)
PFAS(ピーファス)の基準値について
環境省では、2020年に水道水や環境中の水の目標値を、1リットルあたり50ngと定め、飲み水からの摂取を防ぐ取組を進めています。この数値は、人が毎日2リットルを一生飲み続けても、健康への悪影響が生じないと考えられるレベルとされています。
※ng(ナノグラム)=10億分の1グラム
また、環境中に排出されたPFASの一部が、排水処理の過程で発生する汚泥に移行するとの報告があったことから、農林水産省では、汚泥を使った堆肥の分析法を開発し、公定法として2021年に公表しました。
2024年6月には、内閣府食品安全委員会において、PFASの食品健康影響評価が取りまとめられ、PFOS及びPFOAのそれぞれについて、耐容一日摂取量(TDI:人が一生涯にわたって毎日摂取し続けても健康への悪影響がないと推定される一日あたりの摂取量)を、20ng/kg 体重/日 と設定されました。
仮に、農林水産省が全国の事業所から収集した汚泥肥料86点の分析結果の内、PFOS及びPFOAの濃度が最も高い濃度(250μg/kg)を示した汚泥肥料を、長期間連用した圃場で生産された農作物を毎日食べ続けるなど、現在得られている知見をもとに保守的に試算しても、上記TDIを超過することはないと考えられます。
農林水産省は今後、汚泥肥料のPFASに係る科学的知見が不足していることから、農地土壌から農作物への移行に関する研究や、農地土壌におけるPFASの蓄積性などに係る情報収集を進め、科学的知見をさらに蓄積していくこととしています。
PFOS・PFOAとは
そもそもPFOS・PFOAとは、「有機フッ素化合物(PFAS(ピーファス))」の一種であり、有機フッ素化合物とは、炭素とフッ素の結合をもつ有機化合物です。そのうち、ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物を総称して「PFAS」と呼び、10,000種類以上の物質があるとされています。
PFOS(ピーフォス)は「ペルフルオロオクタンスルホン酸」といい、メッキ処理剤や泡消火薬剤などに、PFOA(ピーフォア)は「ペルフルオロオクタン酸」といい、撥水材や界面活性剤などに、2000年代初めごろまで、さまざまな工業や、私たちの身の回りの製品を作る際に使われていました。
2009年以降、環境中での残留性や、健康影響の懸念から、国際的に規制が進み、現在では、日本を含む多くの国で製造・輸入等が禁止されています。
国内では新たに作られることは原則ありませんが、分解されにくい性質があるため、今も環境中に残っています。
長和町の今後の対応について
町では、今回の分析結果を踏まえ、汚泥堆肥の原料である、「生ごみ」「下水汚泥」「し尿汚泥」のそれぞれについて分析を行い、PFASの特定に努めてまいります。
また、分析結果がまとまり次第、公表の予定としております。
この記事に関するお問い合わせ先
住民生活課 環境温暖化対策係
〒386-0603
長野県小県郡長和町古町4247番地1
電話番号:0268-75-2081
お問い合わせはこちら







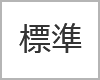
更新日:2025年04月11日